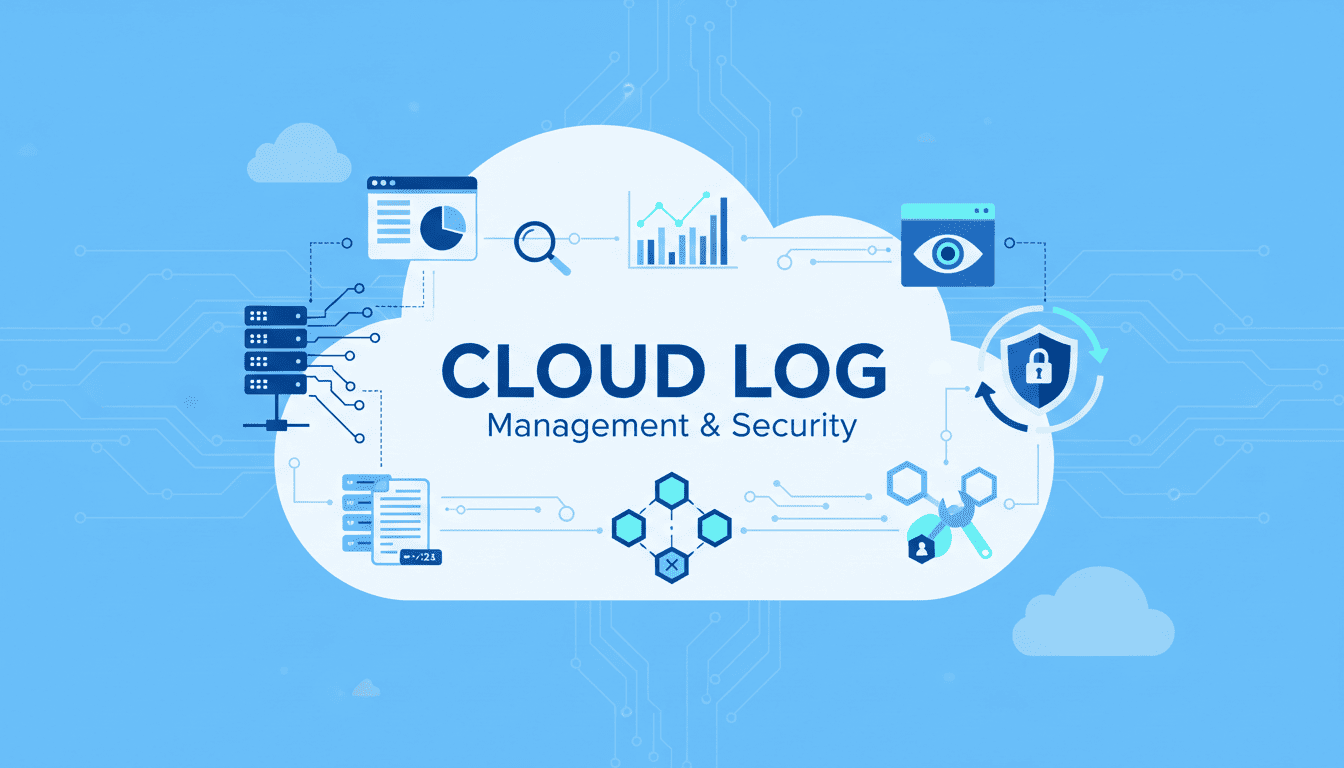記事公開日
データの一元管理が実現!Pleasanter×クラウドDB連携の基本と活用例

はじめに:データ分散が生む非効率とクラウド連携の必要性
中小企業の多くでは、日々の業務でExcelや紙の帳票、さらには部門ごとの業務システムを併用しています。営業部は顧客管理表をExcelで作り、製造部は在庫情報を別システムで管理し、経理は会計ソフトを利用する──。このようにデータがバラバラに存在する「分散管理」の状態では、最新情報の把握や分析が極めて困難になります。たとえば、「最新の売上情報を知りたい」「製造原価の変動を確認したい」といったときに、複数のファイルを開いて照合しなければならず、ミスや遅れが発生します。
こうした課題を解消する鍵が、Pleasanter(プリザンター)とクラウドデータベース(DB)の連携です。Pleasanterは、プログラミング不要で業務アプリを構築できるローコード開発ツール。クラウドDBと組み合わせることで、情報の一元管理・自動同期・可視化を実現できます。本記事では、データ分散の課題から、Pleasanter×クラウドDBによる効率化の仕組み、導入効果までを体系的に解説します。
データの分散が引き起こす非効率
データが各部署・ツールに分散していると、情報の鮮度・整合性・信頼性が大きく損なわれます。ここでは、具体的な問題点を見ていきましょう。
属人化・重複管理の課題
多くの中小企業では、担当者ごとに「自分用の管理ファイル」を作っているケースが少なくありません。同じ取引先情報が営業部、経理部、総務部でそれぞれ管理され、どれが最新なのか分からなくなる状況です。
このような属人化・重複管理が続くと、情報更新の遅れによる誤発注・請求漏れ、退職・異動によるデータ引き継ぎミス、バージョン管理の不整合といったトラブルが頻発します。つまり、「人に依存する情報管理」は業務リスクとコスト増を同時に生むのです。
検索・集計の手間と分析精度の低下
データが複数の場所に分かれていると、必要な情報を探すだけでも時間がかかります。営業担当が「最新の在庫数」を確認したい場合、製造部に問い合わせてExcelを送ってもらい、さらに自分の表に転記する──といった非効率な手順を踏むケースもあります。また、集計時にデータ形式がバラバラだと、正しい分析ができません。数字の単位や表記ゆれが原因で、経営判断に誤差が生じることすらあります。一元管理されていない環境では、スピーディな意思決定は不可能です。
システム連携の不在による業務停滞
販売管理システムと在庫システム、会計システムが連動していない──。このような状態では、1つの変更を反映するために複数システムへ手入力する必要が生じます。たとえば、「出荷データを更新したら会計にも反映する」という単純な処理でも、人手が介在することで二重登録・転記ミスが発生します。手作業を減らし、リアルタイム連携を実現するには、システム間のデータ共有基盤が不可欠です。
DX推進を妨げる「データのサイロ化」
「データのサイロ化」とは、各部署が独自の仕組みでデータを保有し、他部門と共有できない状態を指します。サイロ化が進むと、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が止まってしまいます。なぜなら、AI分析・BIダッシュボード・自動化ツールといったDX施策は、統合されたデータを前提としているからです。つまり、DXの第一歩は「データを集めること」ではなく、「データをつなぐこと」なのです。
外部DB連携による情報集約の考え方
データの分散を解消するためには、「全ての情報を中央に集約し、リアルタイムで更新できる仕組み」が必要です。その解決策が、クラウドDBとの連携です。ここでは、その考え方と設計のポイントを解説します。
クラウドDB連携のメリットとは
クラウドDBを活用すれば、各システムやアプリから発生したデータを1か所に集約し、リアルタイムでアクセス可能な状態にできます。代表的なメリットは以下の通りです。
| 項目 | メリット |
|---|---|
| データ更新 | 常に最新情報を自動反映 |
| コスト | サーバー不要で初期費用を抑制 |
| セキュリティ | クラウドベンダーによる高度な保護 |
| スケーラビリティ | 事業拡大に応じて柔軟に拡張可能 |
この環境をPleasanterと接続することで、現場主導の業務アプリでも「クラウド一元化」を実現できます。
Pleasanter×DB連携の全体像
PleasanterにはAPIやWebhookなど、外部システム連携を支援する機能が豊富に備わっています。クラウドDBと連携することで、例えば以下のようなデータフローが構築可能です。
- 各部署のPleasanterアプリから入力されたデータをクラウドDBへ送信
- クラウドDB上で自動集計・分析
- BIツールやダッシュボードにリアルタイム反映
このように、Pleasanterを「現場入力のハブ」として位置付けることで、全社的なデータ活用が容易になります。
データ構造の整理と正規化のポイント
効率的に連携するためには、まずデータ構造の整理が必要です。たとえば、「顧客情報」「受注データ」「在庫マスター」がそれぞれ独立して存在する場合、共通のキー(顧客IDなど)を設定して紐づけることが重要です。この作業を「データの正規化」と呼びます。重複データを減らし、更新漏れを防ぐことで、クラウドDB連携後も整合性を保ちやすくなります。
セキュリティとアクセス権限の考慮
外部DB連携では、セキュリティ設計を軽視できません。アクセス権限を明確に設定し、Pleasanterの「ロール管理機能」を活用して、部署ごとに閲覧・編集範囲を制限しましょう。また、クラウドDB側でも「IP制限」「SSL通信」「監査ログ」を設定することで、情報漏えいリスクを最小化できます。
Azure・Google・PostgreSQLなどとの連携方法
Pleasanterは、主要なクラウドDBサービスと幅広く連携可能です。ここでは、代表的なサービスの特徴と、具体的な連携イメージを紹介します。
主要クラウドDBサービスの特徴比較
| サービス名 | 特徴 | 適用シーン |
|---|---|---|
| Azure SQL Database | Microsoft製でOffice系連携に強い | 既にMicrosoft 365を導入している企業 |
| Google Cloud SQL | 管理負担が少なくスケーラブル | 変動の多い業務データ管理 |
| Amazon RDS | 複数DBエンジン対応 | 複数サービスを横断的に利用 |
| PostgreSQL | 無料・高性能なOSS | コストを抑えたい中小企業 |
PleasanterとAzure SQL Databaseの連携例
Pleasanterでは、ODBCやAPI経由でAzure SQL Databaseと接続できます。接続手順の一例は以下の通りです。
- AzureポータルでSQL Databaseを作成
- 接続情報(サーバー名・認証情報)を取得
- Pleasanterの「外部DB接続設定」画面に登録
- データマッピングを設定して同期開始
こうした連携により、Pleasanter側で登録したデータが自動的にAzure上のDBへ反映され、リアルタイムに分析・閲覧できます。
Google Cloud SQL連携によるスケーラビリティ強化
Google Cloud SQLは、負荷分散と自動スケールに優れたクラウドDBです。アクセス集中時でも自動でリソースを拡張し、安定稼働を維持できます。PleasanterをGoogle Cloud SQLに接続することで、大量データを扱う業務でも安定性と速度を両立できます。特に在庫管理やIoTデータ連携といった高頻度更新にも対応可能です。
PostgreSQL+Pleasanterで社内外データ統合
PostgreSQLは、コストを抑えたい中小企業にとって理想的な選択肢です。オープンソースでありながら高いパフォーマンスを誇り、Pleasanterの標準データベースとしても利用されています。社内DBとクラウド上の分析環境をPostgreSQL経由でつなぐことで、営業・生産・会計データを一元的に分析可能です。
API活用による自動データ連携
Pleasanterの魅力の一つが、APIを使った外部連携の柔軟性です。API(Application Programming Interface)を活用すれば、システム間のデータ連携を自動化できます。
API連携の基本と仕組み
APIとは、異なるシステム間でデータをやり取りするための“共通の言語”です。PleasanterのAPIを利用すれば、他システムにデータを送信・取得し、日次更新やレポート出力を自動化できます。たとえば「受注が登録されたら在庫システムを更新する」といった業務を、ボタン一つで自動実行することが可能です。
定期バッチ処理とリアルタイム同期の違い
| 方式 | 特徴 | 向いている業務 |
|---|---|---|
| バッチ処理 | 定期的(例:毎晩)にまとめて更新 | 日次・週次更新の定型業務 |
| リアルタイム処理 | データ発生時に即時反映 | 受注・出荷などタイムリーな業務 |
PleasanterではWebhookを利用することで、リアルタイム通知・更新を実現できます。
ノーコード・ローコードで実現する自動化
API連携と聞くと「開発が大変そう」と思われがちですが、Pleasanterはローコード対応のため、専門知識がなくても設定可能です。UI上でAPIエンドポイントやパラメータを設定するだけで、外部連携を自動化できます。このように、現場担当者でも自動化を進められるのがPleasanterの大きな強みです。
API連携トラブルの防止策
API連携では、接続切れやデータ欠損を防ぐ仕組みが欠かせません。具体的には、エラーログの定期監視、再送制御、HTTPS通信の必須化などのポイントを押さえることで、安定した自動連携環境を維持できます。
一元管理で得られる業務改善効果
データを一元化し、リアルタイムで活用できるようになると、組織全体の業務効率と判断スピードが大きく向上します。
情報共有スピードの向上
部署間の情報共有にタイムラグがなくなり、意思決定のスピードが格段に上がります。たとえば、営業担当が最新の在庫を即座に確認できるようになれば、顧客対応が迅速になります。
ミス削減と業務品質の向上
手入力・転記作業が減ることで、ヒューマンエラーが大幅に削減されます。また、常に正しいデータが共有されるため、社内全体で業務品質が均一化されます。
経営指標の「見える化」と迅速な意思決定
データが一元化されることで、BIツールによるダッシュボード表示が容易になります。KPI、原価率、顧客動向などをリアルタイムで把握でき、経営判断のスピードが上がります。
データ活用による新たな価値創出
一元管理されたデータは、AI分析・需要予測・顧客セグメント分析など、次のステップへと活かせます。つまり、業務改善から経営戦略立案までをつなぐ“データ資産”となるのです。
まとめ:Pleasanter×クラウドDBで実現する「データを活かす経営」
データの一元管理は、単なる効率化施策ではなく、企業の意思決定力を強化する経営基盤です。PleasanterとクラウドDBの連携によって、属人的なExcel管理から脱却し、全社的なデータ活用を実現できます。「まずは一部業務から試したい」「既存システムとの連携を相談したい」という企業は、ぜひ専門ベンダーへ相談してみてください。中小企業こそ、“データを持つ”から“データを活かす”時代へ。Pleasanterとクラウド連携が、その第一歩を支えます。