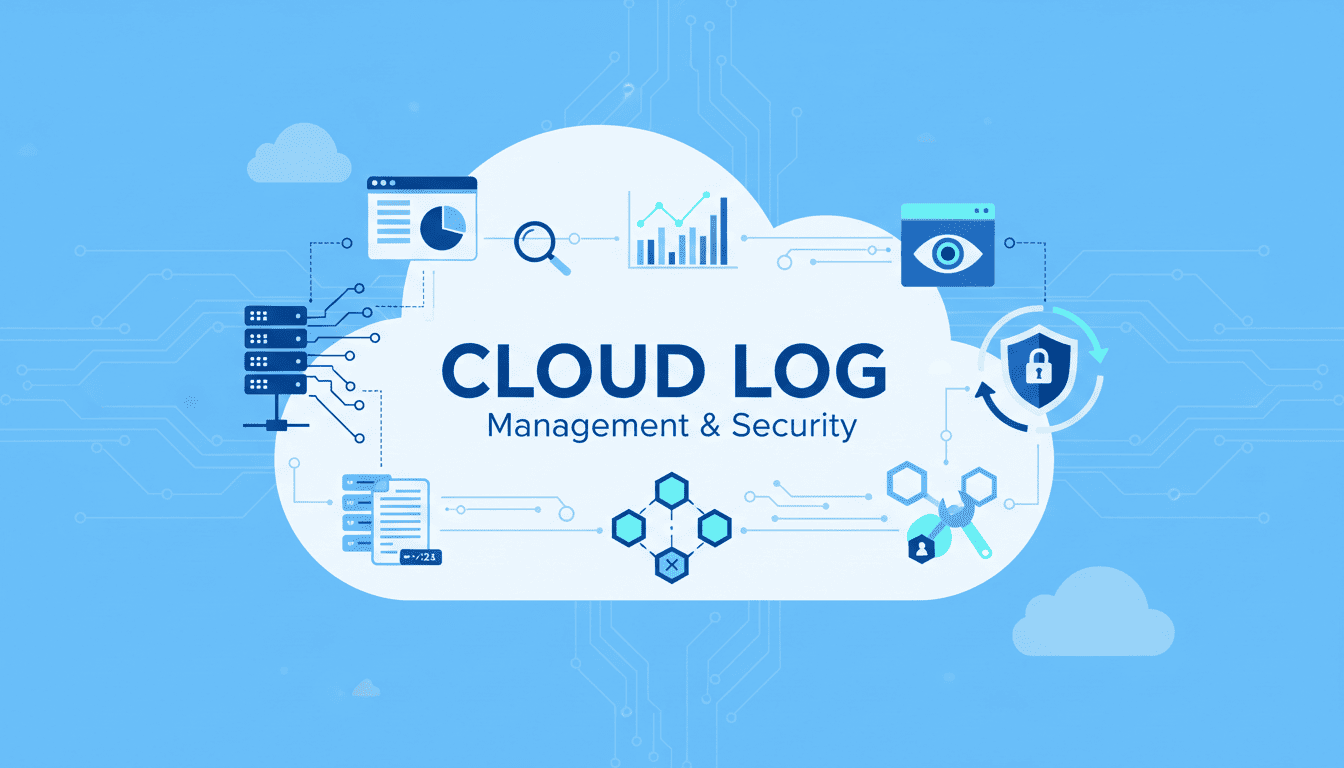記事公開日
最終更新日
コストを抑える!クラウド運用のベストプラクティス ~中小企業が始める“賢いクラウド管理術”~

- はじめに:コストを抑えるクラウド運用とは?
- 不要リソースの削減方法
- 使われていないリソースの見える化と棚卸しのすすめ
- 停止忘れのリソースがコストを生む?スケジューラーの活用法
- 開発環境と本番環境のリソースを切り分ける
- クラウドガバナンスの基本:誰が何を使っているのか?
- コスト監視ツールの活用法
- Azure Cost ManagementやAWS Cost Explorerの基本機能を知ろう
- 月初に確認!請求予測と“想定外の出費”の防ぎ方
- サードパーティ製のマルチクラウド監視ツールも検討
- SlackやMattermostと連携して“見える化”を強化
- 必要最小限のプラン選び
- セキュリティとコストの両立
- 安易なコスト削減が“セキュリティリスク”を招く落とし穴
- セキュリティ機能の“無料”と“有料”の賢い使い分け
- クラウドベンダー任せにしない「自社ルール」の重要性
- 国際ソフトウェアのセキュリティ対応事例(Azure活用)
- 中小企業の成功事例から学ぶクラウド運用
- 製造業での“不要リソース削減”による年間120万円削減事例
- IT担当がいない企業でもできた“自動停止設定”の工夫
- クラウドとチャット連携で“全社のコスト意識”を向上
- 初期費用ゼロで始める!中小企業向け“クラウド最小構成”成功例
- まとめ:中小企業にこそ「クラウドの賢い使い方」が必要
はじめに:コストを抑えるクラウド運用とは?
業務の効率化やテレワークの推進、BCP(事業継続計画)対策などを背景に、クラウドサービスの導入は多くの中小企業で進んでいます。しかし、その一方でこんな声を聞くことも少なくありません。
「毎月の請求額が思ったより高い…」
「誰が何を使っているのか、よく分からない…」
「リソースを整理したいけど、どこから手を付ければ…」
クラウドは柔軟性と拡張性に優れている反面、管理を怠ると“見えない無駄”が積み上がってしまいます。特に中小企業にとっては、限られたIT予算の中で最大限の効果を得るために、コスト最適化は避けて通れない課題です。
本記事では、IT専任担当がいない企業でも実践できる「クラウドの賢い使い方」を、5つのテーマで解説します。不要リソースの削減方法から、便利なコスト監視ツールの活用、セキュリティとの両立、そして成功事例まで――。
クラウド運用の見直しで、大きなコスト削減と業務改善が可能になります。ぜひ自社の環境と照らし合わせながらご覧ください。
不要リソースの削減方法
クラウド環境では、「使っていないけれど放置されている」リソースがコストを押し上げているケースが多々あります。これはクラウド特有の課題で、オンプレミス時代の“使わないサーバは電源を切っておく”という感覚が通用しにくいためです。
この章では、リソースの無駄を洗い出し、計画的に削減するための基本的なアプローチを解説します。
使われていないリソースの見える化と棚卸しのすすめ
クラウドにおける“見えない無駄”の代表例が、放置された仮想マシンやストレージです。テスト用に立てたまま忘れ去られたサーバ、使われていないのに課金が続いているディスクなどが、そのまま毎月の請求に影響します。
見える化の第一歩:「コスト分析ダッシュボード」の活用
主要なクラウドベンダー(例:Microsoft Azure、Amazon Web Services)では、各サービスの使用状況やコストを可視化できるダッシュボード機能が提供されています。
| サービス名 | 主な機能 | 対応クラウド |
|---|---|---|
| Azure Cost Management | リソースごとのコスト分析・アラート・レポート生成 | Microsoft Azure |
| AWS Cost Explorer | 月別・日別の使用状況、フィルタ分析、レコメンド | AWS |
| Google Cloud Billing | 請求のグループ管理、割当制限、傾向分析 | Google Cloud Platform |
このようなツールを使って、「高コストだが利用頻度が低い」「一度もアクセスされていない」リソースを洗い出すことが可能です。
棚卸しのポイント
リソースの棚卸しを行う際には、以下の点に注意しましょう:
-
誰がいつ作成したのか(部署・担当者が分かるようにタグを設定)
-
利用目的は何か(本番/テスト/検証など)
-
直近のアクセス日時(ログを参考にする)
-
自動停止やスケジュール設定の有無
こうした情報をExcelやスプレッドシートなどで一覧化しておくと、次回以降の管理も容易になります。
定期実施がカギ
棚卸しは一度きりではなく、月1回や四半期ごとのルーティン業務として定着させるのが理想です。小規模な企業であっても、定期的な振り返りで無駄な支出を確実にカットできます。
停止忘れのリソースがコストを生む?スケジューラーの活用法
クラウドの利用において意外と見落とされがちなのが「サーバーの停止忘れ」です。開発や検証に使っていた仮想マシンを、夜間や休日にも稼働させたままにしておくと、その分だけ課金が発生してしまいます。
スケジューラーで自動停止を実現
多くのクラウドサービスでは、仮想マシンやリソースの起動・停止をスケジュール設定できます。たとえば以下のような自動化が可能です:
| 曜日 | 時刻 | 操作内容 |
|---|---|---|
| 月~金 | 9:00 | 仮想マシン起動 |
| 月~金 | 19:00 | 仮想マシン停止 |
| 土日 | 終日 | 停止維持 |
これにより、夜間や週末の「無駄な稼働」を排除できます。
設定の一例:Azure Automationによるスケジューリング
Azureを例に挙げると、「Azure Automation」機能を使って以下のような処理を構築できます。
-
「Runbook」を作成(スクリプト形式で起動/停止処理を定義)
-
「スケジュール」機能で曜日・時刻を指定
-
対象VMを指定して自動停止を実行
※難しく感じる場合は、国際ソフトウェアのようなIT支援パートナーに構築支援を依頼するのも有効です。
スケジューラー導入のメリット
-
IT担当者の手間を省き、人的ミスを防止
-
稼働時間の短縮により、電気代・運用コストも間接的に削減
-
利用実態に即したメリハリのあるクラウド活用が可能に
中小企業こそ、こうした小さな工夫を積み重ねることで、大きな節約効果を得られます。
開発環境と本番環境のリソースを切り分ける
クラウド環境の利用が進むと、開発・検証・テスト・本番といった複数の目的でリソースを立てる機会が増えます。このとき重要なのが、それぞれのリソースを明確に分けて管理することです。混在状態を放置すると、コストもリスクも見えづらくなります。
よくある課題:テスト用リソースの“放置課金”
開発担当者が一時的に使った仮想マシンやデータベースをそのまま残しておくと、稼働していなくてもストレージ課金が継続します。たとえば、20GBのSSDディスクが数本残っているだけでも、1年で数万円になることも。
本番・開発環境の分離管理のポイント
-
リソースグループを分ける(Azure、AWS、GCPなど共通のベストプラクティス)
-
命名ルールを統一する(例:
dev-●●●、prod-●●●など) -
課金タグを付ける(例:
Env=Test/Env=Production) -
停止スケジューラーを開発環境に限定して導入する
このような設計により、リソースの所在や目的が一目でわかるようになります。
フローで見るクラウドリソース整理の例
① 利用目的を定義 → ② グループ・命名・タグで分類 → ③ 使用頻度で棚卸し → ④ 不要リソースは停止or削除
クラウドは使い方次第で、「柔軟さ」が「無秩序」になるリスクもあるため、ルールを決めて定着させることが重要です。
クラウドガバナンスの基本:誰が何を使っているのか?
クラウド利用が社内に広がるにつれて、「誰が」「どの部署が」「何の目的で」使っているのか分からなくなるという事態が起きやすくなります。この状態を放置しておくと、不要なリソースの乱立や責任の所在が不明確なコスト発生につながります。
クラウドガバナンスとは?
「ガバナンス」とは、クラウド環境を戦略的かつ統制された方法で管理する仕組みです。特に中小企業では、ガバナンスの整備によって、少人数でも効率的な運用が可能になります。
中小企業向けガバナンスの基本施策
| 項目 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| アクセス権管理 | 管理者/開発者/閲覧者などのロール設定 | 不正操作や誤操作を防止 |
| リソースの命名ルール | 一目で用途が分かるように統一 | 可視性と棚卸しのしやすさ向上 |
| タグ管理 | 所属部署・用途・利用者名などを明記 | コスト分析・責任所在の明確化 |
| 定期レビュー | リソースと権限を定期的に見直す | 利用状況の最適化と不要物の除去 |
「タグ運用」の重要性
AzureやAWSでは、リソースに「タグ」という任意情報を付与できます。たとえば:
タグ:Department=Sales / Project=WebRenewal / Owner=Suzuki
このようにしておくと、コストダッシュボードで「営業部の使用料」や「Suzukiさんの担当プロジェクト」にかかっている費用を可視化できます。
ガバナンスを整えることで、コスト削減だけでなく、社内の責任分担や運用効率の向上にもつながります。
コスト監視ツールの活用法
クラウドにおけるコスト最適化を進めるうえで、“現在何にいくら使っているか”を把握することが最も重要です。これは財務や経理だけでなく、現場のIT担当者にも求められる視点となっています。
幸いにも、AzureやAWSなど多くのクラウドベンダーは、無料で使えるコスト管理ツールを提供しています。さらに、マルチクラウドを監視できる外部サービスや、社内チャットと連携する手法も広がっています。
この章では、実際に使えるツールと、具体的な活用法をご紹介します。
Azure Cost ManagementやAWS Cost Explorerの基本機能を知ろう
まず注目したいのが、各クラウドに標準搭載されている「純正のコスト管理ツール」です。特別な契約や費用が不要で、すぐに使えることが大きな魅力です。
主な機能比較(Azure / AWS)
| 機能 | Azure Cost Management | AWS Cost Explorer |
|---|---|---|
| 日次コストの表示 | 〇 | 〇 |
| タグ・サービス別フィルタ | 〇 | 〇 |
| 予算設定・アラート | 〇 | 〇 |
| コスト分析グラフ | 〇 | 〇 |
| 月別比較レポート | 〇 | 〇 |
活用シーン
-
コストの“高騰要因”を特定したいとき
-
利用傾向の可視化により、ピーク時間や非効率な時間帯を分析したいとき
-
部署ごと・用途ごとのコスト配分を把握したいとき
具体的な使い方(AWS Cost Explorerの例)
-
AWSコンソールで「Billing」→「Cost Explorer」を開く
-
「日別」「サービス別」「リージョン別」などでフィルタを設定
-
グラフ形式でコストの推移を確認
-
「予算の作成」で、特定の閾値に到達したらメール通知を設定
このように、“見える化”と“アラート”がセットになっている点が、純正ツールの大きな強みです。
月初に確認!請求予測と“想定外の出費”の防ぎ方
クラウド運用において多くの中小企業が直面するのが、「気づいたら予算をオーバーしていた」という状況です。これを未然に防ぐには、月初に請求予測と前月実績をチェックする習慣を持つことが重要です。
予算管理の3ステップ
-
予算を設定する
AzureやAWSの管理画面で、月間の上限額を設定できます。設定金額の○%に達したら通知される機能もあります。 -
実績を確認する
前月・前年同月比のコスト推移をグラフで確認し、傾向を把握します。 -
予測と差異を分析する
「どのサービスが予想外に増えているか?」をチェックし、対策を考えます。
表:Azureでの予算アラート設定の流れ(例)
| ステップ | 操作内容 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| ① 予算作成 | サブスクリプションを選び、金額を設定 | 約3分 |
| ② アラート条件設定 | 閾値(例:80%)とメール通知先を設定 | 約5分 |
| ③ 月次確認 | 実績レポートの確認と傾向分析 | 毎月10分程度 |
こうした作業を月初のルーティンに組み込むだけで、クラウド費用の“予兆”をつかめるようになり、対応が早くなります。
注意点
-
アラート設定しても、通知メールを見落とせば意味がないため、チャット連携や社内共有もおすすめです。
-
月初に「請求書を見る」だけでなく、「分析する習慣」が重要です。
サードパーティ製のマルチクラウド監視ツールも検討
AWSとAzure、あるいはGCPとSaaSなど、複数のクラウドを併用する“マルチクラウド環境”が増えています。その際、各社の純正ツールでは横断的なコスト管理が難しいという課題が浮上します。
そこで注目されるのが、マルチクラウド対応のコスト最適化ツールです。
おすすめの外部ツール(国内導入事例あり)
| ツール名 | 特徴 | 対応クラウド |
|---|---|---|
| CloudHealth by VMware | 詳細なコスト分析・レポート自動化 | AWS, Azure, GCP |
| CAST AI | 自動スケーリングとコスト削減提案 | GCP, AWS, Azure |
| OpsCompass | コンプライアンスとコストの統合管理 | AWS, Azure 他 |
-
各クラウドのコストを1つの画面で管理
-
無駄なリソースをAIが自動検出・提案
-
予算超過の原因追跡がスムーズ
導入検討のポイント
-
月間クラウド支出が数十万円を超えてきたら導入を検討
-
社内にIT管理者が少ない場合、運用支援付きプランのある製品を選ぶと安心
無料トライアルがある製品も多いため、まずは実際に触ってみるのがおすすめです。
SlackやMattermostと連携して“見える化”を強化
コスト管理ツールを導入しても、情報が「一部の担当者の頭の中だけ」で止まっていては、社内全体のコスト意識は変わりません。そこで効果的なのが、チャットツールと連携して“見える化”を社内共有する方法です。
例:SlackやMattermostとの連携
-
AWS Budgets → Lambda → Webhook → Mattermost通知
-
Azure Monitor → Logic Apps → Slack投稿
このような構成で、たとえば「今月のクラウドコストが80%を超えました」といった通知をリアルタイムで社内チャットに流すことができます。
国際ソフトウェアでの活用事例(Mattermost)
国際ソフトウェアでは、Mattermostを活用して以下のような仕組みを構築しています:
-
月次レポートを自動生成し、Mattermostチャンネルに投稿
-
各部署の使用状況を定例ミーティングで共有
-
担当者が気づきやすくなり、部門ごとのコスト意識が向上
「コスト管理=バックオフィスの仕事」と考えず、全社で取り組む姿勢が無駄な支出を抑える鍵となります。
必要最小限のプラン選び
クラウド導入の初期にありがちなミスの一つが、「とりあえずハイスペックにしておこう」という過剰投資です。しかし中小企業にとって重要なのは、“必要最低限の機能で最大の効果”を得ること。
この章では、スモールスタートを前提とした最適なクラウドプランの選び方を解説します。
クラウドプランの“選びすぎ”がコスト増を招く
多くの中小企業が、クラウドを導入した際に最初から「ミドル以上の構成」を選んでしまい、結果として過剰なリソースが遊んでいる状態になっているケースは少なくありません。
なぜ“選びすぎ”が起こるのか?
-
ベンダーのおすすめプランに流されがち
-
「今後の拡張を考えて…」と余分なスペックを想定
-
運用開始後に縮小するのが面倒と感じている
このような思考パターンによって、実際には月数時間しか使わないサーバに月数万円かけてしまうということも。
スモールスタートのメリット
| 比較項目 | スモールスタート | ハイスペック導入 |
|---|---|---|
| 月額コスト | 低く抑えやすい | 高額になりやすい |
| 拡張性 | 必要時に拡張可能 | 初期からオーバースペック |
| 検証のしやすさ | 小さく試せる | コストが気になって試せない |
具体例:Webサーバーを構築する場合
-
初期:B1S(Azure)やt3.micro(AWS)などの無料枠や低スペックプラン
-
実運用フェーズ:アクセス数や負荷に応じて段階的に拡張
こうした段階的導入によって、無駄なく、自社に合ったクラウド運用が可能になります。
従量課金 vs 定額課金:どちらが得か?
クラウドの料金体系には、大きく分けて**「従量課金(Pay-as-you-go)」と「定額課金(Reserved/月額固定)」**の2種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の利用パターンに応じた選択が重要です。
比較表:従量課金と定額課金の特徴
| 項目 | 従量課金(都度課金) | 定額課金(予約制・サブスクリプション) |
|---|---|---|
| コストの柔軟性 | ◎(使った分だけ) | △(未使用分も請求) |
| 初期コスト | なし | 1年・3年分を先払いする場合もあり |
| 管理のしやすさ | △(変動が多い) | ◎(予算計画が立てやすい) |
| 利用シーン | テスト・短期利用に最適 | 長期安定利用に最適 |
どちらを選ぶべきか?判断ポイント
-
短期間・一時的な利用 → 従量課金で様子を見るのが吉
-
毎月ほぼ同じ稼働状況 → 定額課金の方が結果的に安くなる
-
予算の見通しが必要な場合 → 定額課金で予測可能な費用管理を
たとえば、営業支援アプリを社内ポータルとして運用する場合、アクセス時間が平日9〜18時に集中すると分かっていれば、定額プラン+スケジューラー停止で効率よく運用できます。
ハイブリッド運用も視野に
一部は従量課金で柔軟に対応しつつ、基幹システムや業務ツールは定額プランでコスト安定させる「ハイブリッド構成」も、現実的な選択肢です。
中小企業におすすめの“軽量構成”テンプレート
クラウドを「小さく始める」には、どのような構成が適しているのでしょうか?ここでは、実績のある中小企業向け軽量テンプレートをご紹介します。
テンプレート例:業務ポータルサイト構成(Azure)
| 要素 | サービス | プラン例 | 月額目安 |
|---|---|---|---|
| Webサーバー | Azure App Service | B1(1コア、1.75GB) | 約1,400円 |
| データベース | Azure SQL Database | Basic(5DTU) | 約550円 |
| ストレージ | Azure Blob Storage | Hot Tier(100GB) | 約250円 |
| 認証 | Azure AD Free | 無料 | 0円 |
**月額:約2,200円〜**で、社内利用に十分なシステムが構築可能です。
軽量構成の導入ポイント
-
初期は最小構成で動作確認
-
実際の負荷や業務要件を見て、段階的にスケールアップ
-
ストレージやバックアップは重要データを優先して確保
無理に“完璧な構成”を目指すより、使いながら調整できる柔軟性を活かすのがクラウド運用の肝です。
クラウド導入前に「用途」を明確にするチェックリスト
クラウド導入において「何のために導入するのか」が曖昧なまま進めると、プラン選びがブレて無駄なコストに直結します。そこで、事前に明確にしておきたいポイントを以下に整理しました。
クラウド導入前の確認チェックリスト
| 質問項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 目的は何か? | 業務改善?システム刷新?BCP対策? |
| 想定利用者は? | 社内限定?取引先も含む? |
| 稼働時間帯は? | 常時稼働?平日9〜18時? |
| 想定データ量は? | 月数GB?数十GB?それ以上? |
| 利用期間は? | 一時的(半年)?恒久的? |
| 必要なセキュリティレベルは? | 外部公開なし?社外接続あり? |
セキュリティとコストの両立
クラウドコストの削減に取り組む際、注意すべきなのが「セキュリティとのバランス」です。“安かろう悪かろう”になっては本末転倒であり、特に情報資産を扱う企業にとってはリスクが非常に高くなります。
この章では、コストとセキュリティをどう両立するかをテーマに、実践的な方法を紹介します。
安易なコスト削減が“セキュリティリスク”を招く落とし穴
「セキュリティ機能は高いから…」「ファイアウォール設定は後回しに…」
こうした判断が、後に大きなトラブルを招く原因になります。情報漏えいやランサムウェア攻撃の多くは、設定の甘さが原因です。
中小企業が陥りがちな失敗例
-
管理者アカウントに多要素認証(MFA)を設定していない
-
クラウド上に誰でもアクセスできるファイルを放置
-
不要なポート(例:3389, 22)を開けっ放し
これらの事例は、“コスト削減を優先した結果”としてよく起こるパターンです。
最低限必要なセキュリティ対策
| 対策項目 | 内容 | コスト |
|---|---|---|
| MFA(多要素認証) | 管理者や開発者のアカウントに設定 | 無料(Azure AD Free等) |
| NSG/セキュリティグループ | 不要ポートをブロック | 無料 |
| ログ監視・アラート設定 | 不審なアクセスの早期検知 | 無料〜 |
| バックアップの自動化 | データ喪失に備える | 月額数百円〜 |
重要なのは、「安くてもできることはある」という視点を持つことです。
セキュリティ機能の“無料”と“有料”の賢い使い分け
クラウドセキュリティ=高コストという印象を持たれがちですが、実は無料で使えるセキュリティ機能も豊富に存在します。これらを上手に活用することで、最低限のセキュリティをコストを抑えて確保することが可能です。
無料で使える主なセキュリティ機能
| ベンダー | 無料機能の例 | 内容 |
|---|---|---|
| Azure | Azure AD Free | ユーザー管理・MFA(一部制限) |
| AWS | IAM, Security Groups | 権限管理、ファイアウォール |
| Google Cloud | IAM, Cloud Audit Logs | 権限と操作ログ管理 |
| サービス名 | 月額費用目安 | 提供機能例 |
|---|---|---|
| Azure Defender | 約1,000円/リソース〜 | 脆弱性スキャン、脅威検知 |
| AWS GuardDuty | 約0.98USD/GB〜 | 異常検知、マルウェア対策 |
| Microsoft Entra ID P1 | 約900円/ユーザー | 条件付きアクセス、ログ分析 |
-
導入初期:無料機能でMFA・アクセス制御を徹底
-
実運用期:ログ監視や脆弱性検知など業務に応じて段階的に導入
このように、「最初から全部有料で固める必要はない」という視点で計画すれば、セキュリティとコストの両立が可能になります。
クラウドベンダー任せにしない「自社ルール」の重要性
クラウドサービスは高機能で便利ですが、**「契約しただけでは安全にならない」**という事実を忘れてはいけません。設定ミスや使い方のズレによって、セキュリティリスクは簡単に発生します。
なぜ自社ルールが必要か?
-
標準設定ではすべてのリスクをカバーできない
-
担当者が代わると運用ポリシーが失われやすい
-
業種ごとの業務要件に対応する必要がある
最低限整備すべきクラウドルール例
| 分類 | 内容 | 設定の一例 |
|---|---|---|
| アカウント管理 | MFA必須、不要アカウントの定期削除 | 「30日間ログインなし→自動削除」など |
| リソース命名 | 用途・部署・環境を含める | web-prod-sales など |
| タグ運用 | 所属部署、オーナー、利用目的など | Dept=Sales, Owner=Tanaka |
| ログ保存 | 操作ログ・アクセスログの保持期間設定 | 最低90日〜365日 |
国際ソフトウェアのセキュリティ対応事例(Azure活用)
ここでは、クラウド運用におけるセキュリティ強化の実践例として、国際ソフトウェアでの取り組みをご紹介します。
導入背景
-
中小企業へのクラウド導入支援を行う中で、「セキュリティに不安がある」という相談が増加
-
特に医療・製薬・食品業界では情報保護の重要性が高い
実施内容(Azure活用)
-
Azure AD(Free版)+MFA設定による管理者アカウントの強化
-
Azure Security Center(現:Defender for Cloud)による脆弱性アラートの通知
-
Azure MonitorとLogic Appsを連携し、セキュリティイベントをMattermostに通知
導入効果
-
ゼロトラスト的な運用設計を低コストで実現
-
チーム全体でセキュリティ意識が向上
-
顧客からの「セキュリティ対応に安心感がある」との評価が増加
このように、段階的な導入・自動化・社内連携を意識することで、コストを抑えつつ強固なセキュリティ運用が可能になります。
中小企業の成功事例から学ぶクラウド運用
これまでご紹介したベストプラクティスを「実際にどう使われているのか?」という視点でご紹介します。
ここでは、実際にクラウド運用を見直し、コスト削減・業務改善・意識改革を実現した中小企業の成功事例を4つ取り上げます。
製造業での“不要リソース削減”による年間120万円削減事例
企業プロフィール
-
業種:機械部品製造業(従業員60名)
-
導入サービス:AWS(EC2・S3・RDS)
課題
-
テスト環境で使用していたサーバが稼働したまま半年放置
-
退職者が作成したリソースのオーナーが不明
-
毎月の請求が20万円超と高止まりしていた
取り組み内容
-
AWS Cost Explorerで使用状況を可視化
-
全リソースにオーナータグと利用目的タグを付与
-
定期棚卸しのルール化(2ヶ月に1回)
-
開発用サーバにスケジュール停止設定を導入
成果
-
不要リソースを削除+稼働時間の制限により月額10万円以上の削減
-
年間で120万円以上のコストカット
-
情報システム部門の属人性を解消し、運用の可視化と標準化を実現
このように、「見える化+棚卸し+ルール化」が成功の鍵となりました。
IT担当がいない企業でもできた“自動停止設定”の工夫
企業プロフィール
-
業種:食品製造(従業員30名)
-
導入サービス:Microsoft Azure(VM・SQL・Blob Storage)
-
IT専任担当:なし(兼任で経理担当者が管理)
課題
-
開発用VMが夜間・週末も常時稼働しており、無駄なコストが発生
-
使っていないディスクも削除されず、ストレージコストが増加
取り組み内容
-
Azure Automationアカウントを作成
-
PowerShellのテンプレートをベースにVM自動停止のRunbookを設定
-
スケジュール:平日19:00に停止/9:00に起動
-
「タグが“AutoStop対象”のVMのみ対象」として運用管理
結果
-
夜間・休日の無駄な稼働を削減し、月額8,000円以上のコスト削減
-
操作はすべてGUIベースで対応できたため、非エンジニアでも実施可能
-
今では全社のIT資産見直しのきっかけに
「IT担当がいないから無理」ではなく、“簡単にできる工夫”を見つけて始めることが大切だとわかる事例です。
クラウドとチャット連携で“全社のコスト意識”を向上
企業プロフィール
-
業種:建築設計事務所(従業員15名)
-
利用クラウド:AWS(LightSail・S3)、Google Workspace
-
社内ツール:Mattermost
課題
-
クラウドの費用が毎月上昇するが、誰も自分事としてとらえていない
-
経理担当者しか請求明細を見ておらず、原因分析が進まない
取り組み内容
-
AWS BudgetsとLambdaを使ってコスト閾値超え通知をMattermostに自動投稿
-
「今月の費用が90%に達しました」など定型メッセージで可視化
-
全社員が参加するMattermostチャンネルに共有
効果
-
「無駄なVMを落とそう」「ディスク残してたかも」と社員自発の対応が増加
-
毎月のAWS費用が15〜20%減少
-
全社員がコスト意識を持つ文化に変化
クラウドコストは、共有すれば“社内で協力して削減できる”性質を持っています。
初期費用ゼロで始める!中小企業向け“クラウド最小構成”成功例
企業プロフィール
-
業種:広告代理店(従業員8名)
-
要件:社内ポータルサイトの構築(ドキュメント共有+掲示板)
実施内容
-
Microsoft Azureの無料枠(12ヶ月間無料+常時無料サービス)を活用
-
利用構成:
-
Azure App Service(無料プラン)
-
Azure SQL Database(5DTU、1ヶ月無料)
-
Azure Storage(Hot Tier、無料枠内)
-
成果
-
初月の利用料金は完全無料
-
2ヶ月目以降も月額1,000円以下の運用を実現
-
社内での情報共有が活発になり、業務効率が改善
ポイント
-
「業務に必要な最小構成は何か?」を徹底的に絞った
-
段階的に使いながら機能を追加
-
将来的にスケールアップしやすい構成にしたことで、拡張性も確保
初期投資ゼロで始められるこのスタイルは、クラウド導入に不安を抱える中小企業のファーストステップとして非常に有効です。
まとめ:中小企業にこそ「クラウドの賢い使い方」が必要
クラウドは、ただ導入するだけでは成果を出せません。「使い方」や「管理の工夫」によって、コストは大きく変動します。
本記事では、以下のようなベストプラクティスをご紹介してきました:
-
不要リソースの見える化と棚卸し
-
スケジューラーによる自動停止
-
タグ管理や予算アラートでのガバナンス強化
-
スモールスタートでのプラン選定
-
無料機能を活かしたセキュリティ確保
-
全社を巻き込んだコスト意識の醸成
これらはすべて、ITに詳しくない中小企業の担当者でも今日から実践できる工夫です。
クラウドは、単なる費用ではなく「利益を生むための資産」。
だからこそ、見直せば見直すほど“リターンが増える”仕組みとも言えます。
「クラウドコストが高い」「使い方が分からない」と感じたときこそ、改善のチャンスです。
ぜひ本記事を参考に、自社に合った“賢いクラウド管理”をはじめてみてください。
国際ソフトウェアでは、中小企業様のクラウド導入・運用に関する無料相談を随時受付中です。
「自社で何ができるか知りたい」「初期構成を一緒に考えてほしい」など、お気軽にお問い合わせください。
| お勧めのクラウドサービスの記事 |
|---|
| 中小企業がクラウドを採用すべき5つの理由 |
| クラウドがなぜDX(デジタルトランスフォーメーション)の第一歩なのか |
| オンプレミスからクラウドへ移行すべきタイミングとは? |
| クラウドって何?中小企業のための基本解説 |
| 従業員の理解と協力を得る!クラウド導入を成功させる社内教育の実践ガイド |
| セキュリティが心配?中小企業が知るべきクラウドのセキュリティ対策とその基本 |